こんにちは!ココカラマニカ編集担当の斎藤です!
梅雨が明ける前から気温も湿度も上がり始めるこの時期。
「元気そうに見えるけど、なんだかボーっとしてる?」「頭が痛いって言ってるけど大丈夫?」
そんなふとした気づきが、お子さんの熱中症のサインかもしれません!
この記事では、子どもの熱中症に気づくためのチェックポイント、病院に行くかどうかの判断基準などはもちろん、毎朝できる予防の工夫まで、まとめてご紹介します。
子どもが熱中症になりやすいのはなぜ?
子どもは大人よりも体温調整機能が未熟で、体の表面積に対して体内の水分量が多いため、熱や水分の影響を受けやすいといわれています。
さらに背が低く地面からの照り返しを受けやすいこともあり、実は思っている以上に体が熱をためこみがちです。
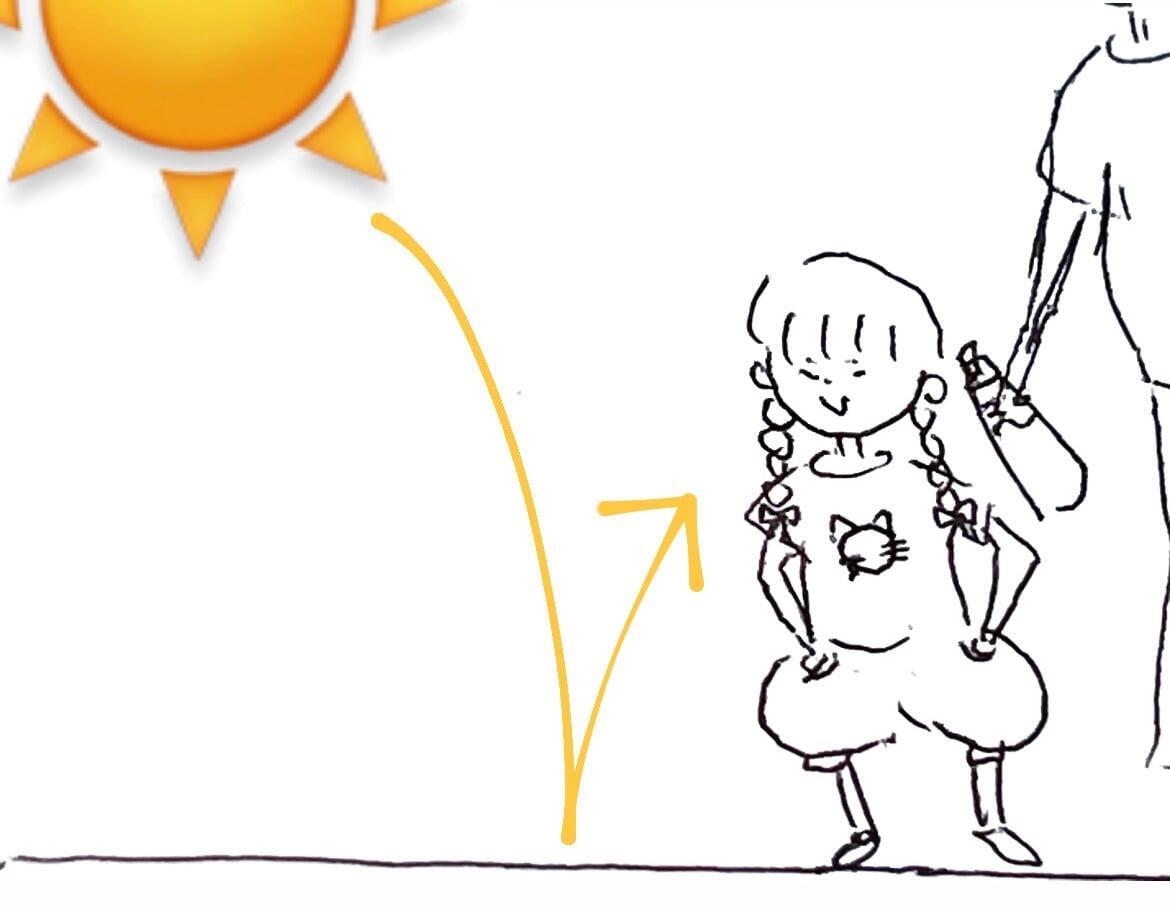
もしかして熱中症?子どもの様子で気をつけたいサイン

病院に行くべき?受診の目安と判断ポイント
特に乳幼児は「暑い」「気分が悪い」と訴えられないため、普段との違いを見逃さないことが大切です。
| 症状 | 対応 |
|---|---|
| 軽い頭痛・倦怠感のみ | 涼しい場所で水分補給しながら様子を見る |
| 水分がとれない、元気がない | 早めに小児科を受診する |
| 意識低下、反応が鈍い、嘔吐・けいれんがある | 迷わず救急要請 |
▶︎スライドしてください▶︎▶︎▶︎
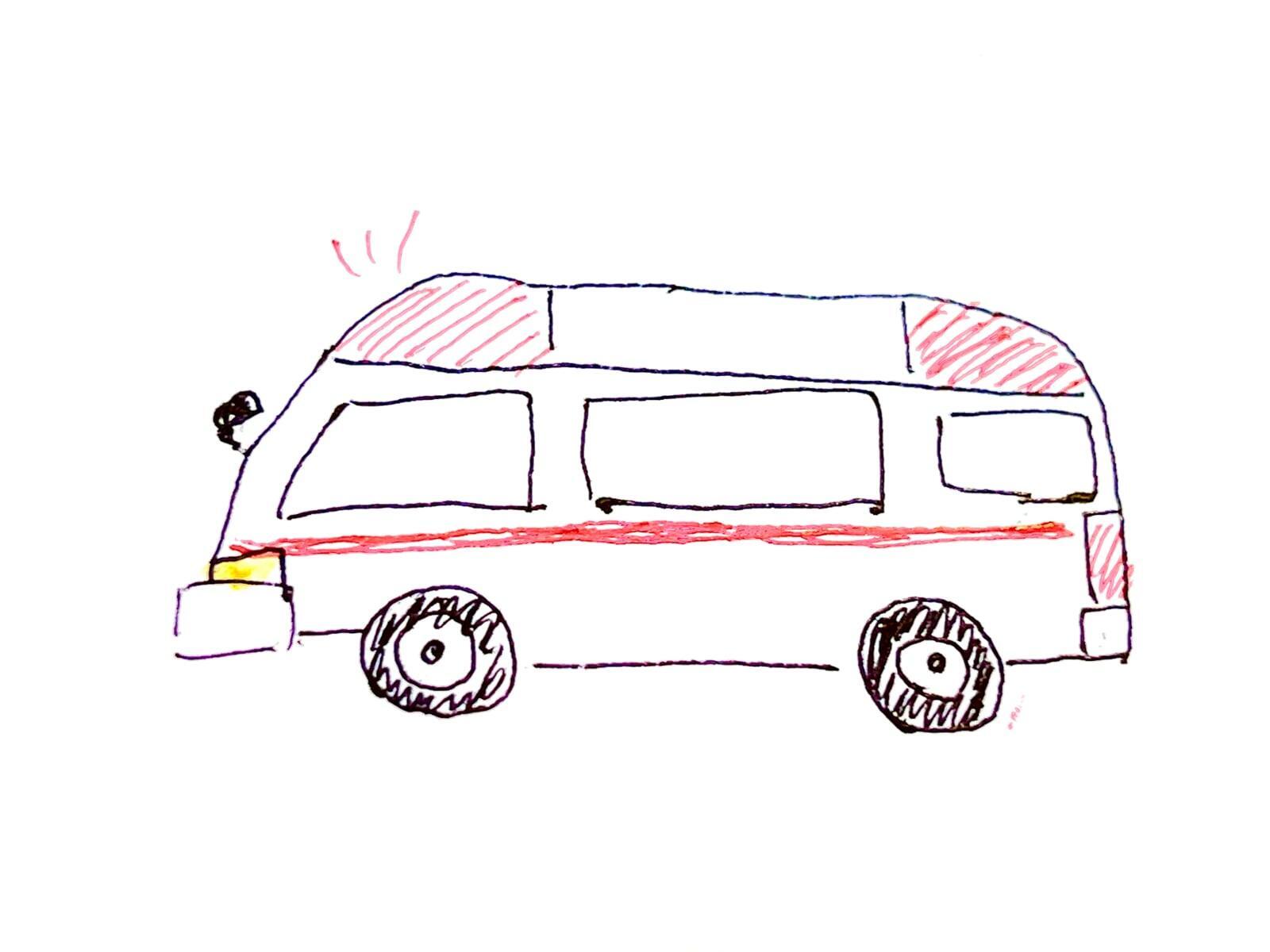
熱中症の頭痛やだるさは何日くらいで治る?
軽い熱中症であれば、1日〜3日程度で改善することが多いですが、無理をすると長引いてしまうこともあります。
以下のような状態が続くときは、再受診をおすすめします。
頭痛やだるさが3日以上続く
食欲が戻らない
発熱が治まらない
夜眠れていない、不機嫌が続いている
朝の送り出しにプラスしたい、暑さ対策のひと工夫
毎日がんばって通う子どもたちに、暑さから守る“ちょっとした工夫”を添えてあげませんか?
時間のない朝でもできること、意外とたくさんあります。
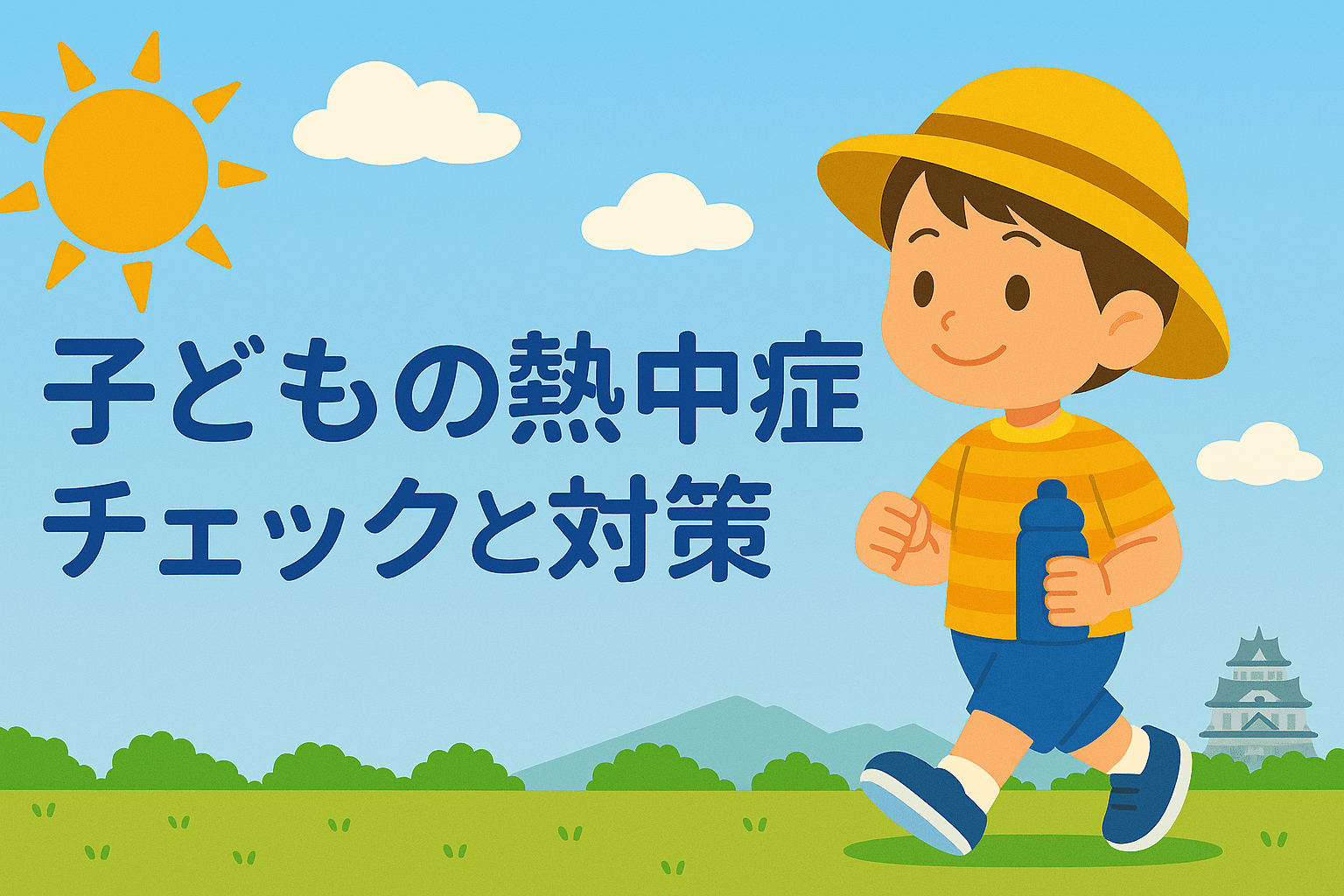
まとめ|「おかしいな?」と思ったら、まずは休ませて
熱中症は、初期なら水分補給と涼しい場所での休息で回復することが多いようですが、タイミングを逃すと重症化するおそれもあります。
特に子ども自身は、不調に気づきにくいからこそ、大人の目と感覚がいちばんの予防策になります!
「ちょっと様子がおかしいな」と思ったら、立ち止まって、休ませてあげてください。その判断が、子どもの夏を守る力になります。

